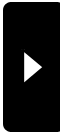2019年10月15日
令和元年10月14日ボランティアガイド活動研修・下見報告
11月9日予定されているイベント『天智天皇ゆかりの大津宮跡を訪ね渡来人の郷を巡る』のガイドの下見兼研修会を行った。
当時は雨模様だったが、10時にJR大津京駅を出発しほぼ予定を達成できた。
コース
JR大津京駅(集合)→近江大津宮跡(内裏南門跡、回廊跡、正殿跡、柵跡など)→ 皇子山古墳 → 近江神宮(昼食) → 南滋賀町廃寺跡 → 百穴古墳群 → 志賀の大仏 崇福寺跡 →桐畑古墳(熊ケ谷古墳群)→古墳公園(太鼓塚古墳群)→ 滋賀里駅(解散)
・近江大津宮跡
JR大津京駅から裏道を通って、京阪近江神宮前駅を経由して最初の近江大津宮跡へ、説明文だけがあり住宅地のようだった。
大津宮は中大兄皇子(天智天皇)が白村江の戦いで負けて、667年に都を飛鳥から近江に移した。
当日2班になった場合は、第二グループはここで近江大津宮について背景、歴史等を説明する。
・大津宮錦織遺跡
昭和49年に発見された内裏南門と回廊の柱跡。 内裏は南北250m、東西160m。 また当時は寺社を除いて、礎石なしで地面から直接柱を立てる方式であり、柱跡が残っていた。

掘っ建て方式の柱であったため、伊勢神宮等のように定期的に遷宮(建て替える)する必要があった。
・皇子山古墳
出土土器類から古墳時代前半と推定され、一号墳が前方後方墳であることから、大和朝廷の影響を受けていない近江の有力者の墓と考えられている。

二号墳は直径約20mの円墳。 いずれも山を利用していて、古市・百舌鳥古墳群のように、盛り土して造ったものではない。
・近江神宮
皇紀2600年の記念事業として昭和15年(1940年)に創建された。
天智天皇が大津宮で水時計(漏刻)を使用して初めて時刻を知らせた由緒から、時計記念館が併設されている。境内には3種類の時計が設置、展示されている。写真は有名な水時計。 一つの時計はなかなか面白かった。

・南滋賀町廃寺跡
大津宮跡調査の一環として発掘調査が行われ、白鳳時代創建の壮大な寺院跡だと分かった。
塔、西金堂(西塔)、金堂、講堂、僧坊を配し、塔と西金堂を回廊で囲むことから奈良飛鳥村川原寺とよく似た伽藍配置(川原寺式)となっている。
東海道遊歩道を通って、百穴古墳群
百穴古墳群には未確認のものを含めて100基以上の古墳があるとされ、この古墳群独特の副葬品が発見されている。

崇福寺に向かう途中に旅の安全を祈念した阿弥陀如来坐像の「志賀の大仏」がある。 先日の台風の為か、山中越えの道は通行禁止となっていた。 結構きつい山道を登って
・崇福寺跡
天智天皇が創建した崇福寺。 北尾根、中尾根、南尾根それぞれに建物があり、中尾根の塔心礎から発見された舎利壺は国宝に指定されている。 写真は塔心礎の場所

南尾根は秋には素晴らしい景観になると思われるが、ここには金堂と講堂があった。 ただ、最近の調査では桓武天皇が天智天皇追慕のために建てた梵釈寺とする説も上がってきている。

天智天皇がお告げを聞いたとされる金仙滝を横に下山。

.・熊ケ谷古墳群(桐畑古墳)
熊ケ谷古墳群には6基の古墳が確認されている。この古墳は最大で有力者の墓と考えられる。 現在不動明王が祀られている。
・太鼓塚古墳群
この辺りにかつて古墳が20基ばかりあって、古墳公園として整備されているが、現在は殆ど宅地化され住宅になっている。 さらに近くの丘陵地にも30基ばかりの古墳が点在していたが、現在は住宅になっている。
解散地点京阪滋賀里駅へ約5分。
道順の大きな間違いもなく、ほぼ初期の目的ができたと思われる。
【お問い合わせ】
おやじのたまり場~セカンドライフサロン~
〒520-0047 大津市浜大津4 丁目1-1 明日都浜大津1F 大津市市民活動センター内
電話&FAX:077-521-7751 E メール :0811salon@gmai l .com
大津市ボランティアセンター
明日都浜大津5F 大津市社会福祉協議会内
電話:077-525-9316 FAX:077-521-0207
文責 山本
、
当時は雨模様だったが、10時にJR大津京駅を出発しほぼ予定を達成できた。
コース
JR大津京駅(集合)→近江大津宮跡(内裏南門跡、回廊跡、正殿跡、柵跡など)→ 皇子山古墳 → 近江神宮(昼食) → 南滋賀町廃寺跡 → 百穴古墳群 → 志賀の大仏 崇福寺跡 →桐畑古墳(熊ケ谷古墳群)→古墳公園(太鼓塚古墳群)→ 滋賀里駅(解散)
・近江大津宮跡
JR大津京駅から裏道を通って、京阪近江神宮前駅を経由して最初の近江大津宮跡へ、説明文だけがあり住宅地のようだった。
大津宮は中大兄皇子(天智天皇)が白村江の戦いで負けて、667年に都を飛鳥から近江に移した。
当日2班になった場合は、第二グループはここで近江大津宮について背景、歴史等を説明する。
・大津宮錦織遺跡
昭和49年に発見された内裏南門と回廊の柱跡。 内裏は南北250m、東西160m。 また当時は寺社を除いて、礎石なしで地面から直接柱を立てる方式であり、柱跡が残っていた。
掘っ建て方式の柱であったため、伊勢神宮等のように定期的に遷宮(建て替える)する必要があった。
・皇子山古墳
出土土器類から古墳時代前半と推定され、一号墳が前方後方墳であることから、大和朝廷の影響を受けていない近江の有力者の墓と考えられている。
二号墳は直径約20mの円墳。 いずれも山を利用していて、古市・百舌鳥古墳群のように、盛り土して造ったものではない。
・近江神宮
皇紀2600年の記念事業として昭和15年(1940年)に創建された。
天智天皇が大津宮で水時計(漏刻)を使用して初めて時刻を知らせた由緒から、時計記念館が併設されている。境内には3種類の時計が設置、展示されている。写真は有名な水時計。 一つの時計はなかなか面白かった。
・南滋賀町廃寺跡
大津宮跡調査の一環として発掘調査が行われ、白鳳時代創建の壮大な寺院跡だと分かった。
塔、西金堂(西塔)、金堂、講堂、僧坊を配し、塔と西金堂を回廊で囲むことから奈良飛鳥村川原寺とよく似た伽藍配置(川原寺式)となっている。
東海道遊歩道を通って、百穴古墳群
百穴古墳群には未確認のものを含めて100基以上の古墳があるとされ、この古墳群独特の副葬品が発見されている。
崇福寺に向かう途中に旅の安全を祈念した阿弥陀如来坐像の「志賀の大仏」がある。 先日の台風の為か、山中越えの道は通行禁止となっていた。 結構きつい山道を登って
・崇福寺跡
天智天皇が創建した崇福寺。 北尾根、中尾根、南尾根それぞれに建物があり、中尾根の塔心礎から発見された舎利壺は国宝に指定されている。 写真は塔心礎の場所
南尾根は秋には素晴らしい景観になると思われるが、ここには金堂と講堂があった。 ただ、最近の調査では桓武天皇が天智天皇追慕のために建てた梵釈寺とする説も上がってきている。
天智天皇がお告げを聞いたとされる金仙滝を横に下山。
.・熊ケ谷古墳群(桐畑古墳)
熊ケ谷古墳群には6基の古墳が確認されている。この古墳は最大で有力者の墓と考えられる。 現在不動明王が祀られている。
・太鼓塚古墳群
この辺りにかつて古墳が20基ばかりあって、古墳公園として整備されているが、現在は殆ど宅地化され住宅になっている。 さらに近くの丘陵地にも30基ばかりの古墳が点在していたが、現在は住宅になっている。
解散地点京阪滋賀里駅へ約5分。
道順の大きな間違いもなく、ほぼ初期の目的ができたと思われる。
【お問い合わせ】
おやじのたまり場~セカンドライフサロン~
〒520-0047 大津市浜大津4 丁目1-1 明日都浜大津1F 大津市市民活動センター内
電話&FAX:077-521-7751 E メール :0811salon@gmai l .com
大津市ボランティアセンター
明日都浜大津5F 大津市社会福祉協議会内
電話:077-525-9316 FAX:077-521-0207
文責 山本
、
令和5年12月2日 「古都大津・歴史 散 策 港町・宿場町大津と大津城跡を巡る」ガイド報告
古都大津・歴史 散 策 港町・宿場町大津と大津城跡を巡る参加者募集
令和5年11月4日 歴史街道ウォーク・天智天皇ゆかりの「近江大津宮跡」を訪ね「渡来人の郷」をゆく
令和5年5月27日 歴史街道ウォーク・まぼろしの保良宮と近江国分寺跡を訪ねる
令和4年11月12日街道ウォーク・琵琶湖疏水その3報告
令和4年11月12日(土) 琵琶湖疎水シリーズ その3参加者募集
古都大津・歴史 散 策 港町・宿場町大津と大津城跡を巡る参加者募集
令和5年11月4日 歴史街道ウォーク・天智天皇ゆかりの「近江大津宮跡」を訪ね「渡来人の郷」をゆく
令和5年5月27日 歴史街道ウォーク・まぼろしの保良宮と近江国分寺跡を訪ねる
令和4年11月12日街道ウォーク・琵琶湖疏水その3報告
令和4年11月12日(土) 琵琶湖疎水シリーズ その3参加者募集
Posted by シニアサロン大津~おやじのたまり場~ at 16:40│Comments(0)
│旧・ポランティアガイド