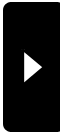2019年06月08日
令和元年6月8日 歴史探訪(湖族の郷堅田を訪ね、小野妹子ゆかりの小野を巡る)報告
5月25日に行われた古都大津・歴史街道探訪(北国海道Ⅲ)『湖族の郷堅田を訪ね小野妹子ゆかりの小野を巡る』に当日堅田駅に集まられたのは38名もの方が集まられ、おやじのたまり場メンバー4名がアテンドさせせいただいた。
コースは以下の通りで、一部説明と写真を付け加えました。 全行程10㎞強
JR堅田駅→堅田内湖
中世の堅田は延暦寺の荘園であったが、堅田衆は自らの手で郷をつくり琵琶湖の水運・漁業の権益を一手に掌握しそこから得た豊富な資金を持って「堅田千軒」と言われる近江最大の自治都市を築き、政治権力から離れて運営していた。 現在内湖では淡水真珠の養殖がおこなわれている。

祥瑞寺
臨済宗大徳寺派の寺院で1406年堅田にあった寺庵が華瘦宗曇に寄進され大徳寺末寺となり、近江の臨済宗の中心的な寺院として栄えた。禅僧として著名な一休が宗純と称していた頃、23歳から13年間宗曇のもと厳しい修行を経て「一休」の道号を与えられた寺でもある。

光徳寺→本福寺
浄土真宗本願寺派の寺院で、14世紀三上神社の神職であった善道が開いた。寛正の法難の時、堅田に逃亡してきた蓮如は本福寺に居を移した。蓮如は全人衆と言われた農民や商工業者から強い支持を受け本福寺は堅田門徒(一向宗)の拠点となった。

満月寺(浮御堂)
浮御堂は臨済宗大徳寺派の寺院で満月寺という。10世紀恵心僧都源信が開いた。現在の浮御堂は昭和9年の室戸台風で倒壊、昭和12年の再建、観音堂の(聖観音坐像)国の重要文化財である。
近江八景の一つ、雁が湖上を飛来するさまをあらわした「堅田落雁」で知られる堅田の景観の中心である。


居初氏庭園
庭園は、17世紀後期につくられ、琵琶湖に接し対岸の三上山などを借景に取り入れ、庭に面して茶室をそなえた奥座敷の性格を持つ茅葺入母屋つくりの建物がある。
出島灯台→野神神社(勾当内侍の墓)
南北朝時代足利尊氏に敗れた新田義貞は、大恋愛の末結婚した妻の勾当内侍を堅田に残したまま北陸へ落ち戦死した。
この悲報を聞いた勾当内侍は悲しみのあまり琵琶湖に身を投げ自殺。村人たちが彼女を哀れんで墓を作り同地に野神神社を立てて氏神とした。

真野の入江→小野妹子神社(唐臼山古墳)→小野道風神社
小野神社飛地境内社の小野道風神社本殿(国指定重要文化財)は三間社切妻造平入(きりずまつくりひらいり)の社殿で南北朝時代に建てられたと言われている

小野神社・小野篁神社・小野小町供養塔
小野神社の境内社で本殿は三間社切妻造平入の形式で1341年頃の建築と考えられており、中世の切妻造平入の本殿は全国的にも珍しく、県下では小野道風神社、天皇神社本殿のわずか三棟しか残っていない。
祭神の小野篁は、平安時代の公卿であり著名な詩人、歌人でもある。また遣唐副使、蔵人頭、参議を務めた政治家でもあり、人物、学識、文才など平安貴族の中でも群を抜いていた。孫の小野小町の供養塔も祀られている。
写真は同神社にあるパワーの木

榎の石碑
古代北陸道では当地は和邇の宿駅があり、江戸時代徳川幕府により全国の街道に一里塚が設けられ、この宿駅にも榎の木が植えられ、旅人の標となっていたが、樹齢360年余りで榎の大木は枯れてしまった。 しかし。昭和43年、有志により榎の宿を偲んで顕彰碑が建てられた。

→JR和邇駅(解散)
暑い中、お一人が所用の為途中で帰られただけで、全員が解散地点の和邇駅まで元気に歩かれ、いい歴史探訪ウォークになりました。
参加された皆様に感謝します。 また、今秋予定されています『天智天皇ゆかりの大津宮跡を訪ね、渡来人の郷を巡る』に、皆様がお誘いあわせの上参加されることを期待してます。
【お問い合わせ】
おやじのたまり場~セカンドライフサロン~
〒520-0047 大津市浜大津4 丁目1-1 明日都浜大津1F 大津市市民活動センター内
電話&FAX:077-521-7751 E メール :0811salon@gmai l .com
大津市ボランティアセンター
明日都浜大津5F 大津市社会福祉協議会内
電話:077-525-9316 FAX:077-521-0207
コースは以下の通りで、一部説明と写真を付け加えました。 全行程10㎞強
JR堅田駅→堅田内湖
中世の堅田は延暦寺の荘園であったが、堅田衆は自らの手で郷をつくり琵琶湖の水運・漁業の権益を一手に掌握しそこから得た豊富な資金を持って「堅田千軒」と言われる近江最大の自治都市を築き、政治権力から離れて運営していた。 現在内湖では淡水真珠の養殖がおこなわれている。

祥瑞寺
臨済宗大徳寺派の寺院で1406年堅田にあった寺庵が華瘦宗曇に寄進され大徳寺末寺となり、近江の臨済宗の中心的な寺院として栄えた。禅僧として著名な一休が宗純と称していた頃、23歳から13年間宗曇のもと厳しい修行を経て「一休」の道号を与えられた寺でもある。
光徳寺→本福寺
浄土真宗本願寺派の寺院で、14世紀三上神社の神職であった善道が開いた。寛正の法難の時、堅田に逃亡してきた蓮如は本福寺に居を移した。蓮如は全人衆と言われた農民や商工業者から強い支持を受け本福寺は堅田門徒(一向宗)の拠点となった。
満月寺(浮御堂)
浮御堂は臨済宗大徳寺派の寺院で満月寺という。10世紀恵心僧都源信が開いた。現在の浮御堂は昭和9年の室戸台風で倒壊、昭和12年の再建、観音堂の(聖観音坐像)国の重要文化財である。
近江八景の一つ、雁が湖上を飛来するさまをあらわした「堅田落雁」で知られる堅田の景観の中心である。


居初氏庭園
庭園は、17世紀後期につくられ、琵琶湖に接し対岸の三上山などを借景に取り入れ、庭に面して茶室をそなえた奥座敷の性格を持つ茅葺入母屋つくりの建物がある。
出島灯台→野神神社(勾当内侍の墓)
南北朝時代足利尊氏に敗れた新田義貞は、大恋愛の末結婚した妻の勾当内侍を堅田に残したまま北陸へ落ち戦死した。
この悲報を聞いた勾当内侍は悲しみのあまり琵琶湖に身を投げ自殺。村人たちが彼女を哀れんで墓を作り同地に野神神社を立てて氏神とした。
真野の入江→小野妹子神社(唐臼山古墳)→小野道風神社
小野神社飛地境内社の小野道風神社本殿(国指定重要文化財)は三間社切妻造平入(きりずまつくりひらいり)の社殿で南北朝時代に建てられたと言われている

小野神社・小野篁神社・小野小町供養塔
小野神社の境内社で本殿は三間社切妻造平入の形式で1341年頃の建築と考えられており、中世の切妻造平入の本殿は全国的にも珍しく、県下では小野道風神社、天皇神社本殿のわずか三棟しか残っていない。
祭神の小野篁は、平安時代の公卿であり著名な詩人、歌人でもある。また遣唐副使、蔵人頭、参議を務めた政治家でもあり、人物、学識、文才など平安貴族の中でも群を抜いていた。孫の小野小町の供養塔も祀られている。
写真は同神社にあるパワーの木
榎の石碑
古代北陸道では当地は和邇の宿駅があり、江戸時代徳川幕府により全国の街道に一里塚が設けられ、この宿駅にも榎の木が植えられ、旅人の標となっていたが、樹齢360年余りで榎の大木は枯れてしまった。 しかし。昭和43年、有志により榎の宿を偲んで顕彰碑が建てられた。
→JR和邇駅(解散)
暑い中、お一人が所用の為途中で帰られただけで、全員が解散地点の和邇駅まで元気に歩かれ、いい歴史探訪ウォークになりました。
参加された皆様に感謝します。 また、今秋予定されています『天智天皇ゆかりの大津宮跡を訪ね、渡来人の郷を巡る』に、皆様がお誘いあわせの上参加されることを期待してます。
【お問い合わせ】
おやじのたまり場~セカンドライフサロン~
〒520-0047 大津市浜大津4 丁目1-1 明日都浜大津1F 大津市市民活動センター内
電話&FAX:077-521-7751 E メール :0811salon@gmai l .com
大津市ボランティアセンター
明日都浜大津5F 大津市社会福祉協議会内
電話:077-525-9316 FAX:077-521-0207
令和5年12月2日 「古都大津・歴史 散 策 港町・宿場町大津と大津城跡を巡る」ガイド報告
古都大津・歴史 散 策 港町・宿場町大津と大津城跡を巡る参加者募集
令和5年11月4日 歴史街道ウォーク・天智天皇ゆかりの「近江大津宮跡」を訪ね「渡来人の郷」をゆく
令和5年5月27日 歴史街道ウォーク・まぼろしの保良宮と近江国分寺跡を訪ねる
令和4年11月12日街道ウォーク・琵琶湖疏水その3報告
令和4年11月12日(土) 琵琶湖疎水シリーズ その3参加者募集
古都大津・歴史 散 策 港町・宿場町大津と大津城跡を巡る参加者募集
令和5年11月4日 歴史街道ウォーク・天智天皇ゆかりの「近江大津宮跡」を訪ね「渡来人の郷」をゆく
令和5年5月27日 歴史街道ウォーク・まぼろしの保良宮と近江国分寺跡を訪ねる
令和4年11月12日街道ウォーク・琵琶湖疏水その3報告
令和4年11月12日(土) 琵琶湖疎水シリーズ その3参加者募集
Posted by シニアサロン大津~おやじのたまり場~ at 21:06│Comments(0)
│旧・ポランティアガイド